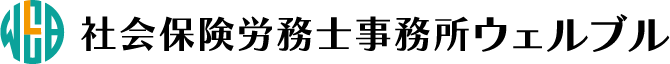2025年4月1日に施行された育児・介護休業法の改正、皆様の会社では既に対応はお済みでしょうか。
もし、まだ対応が完了していない会社様がいらっしゃれば、本記事をご覧になり早急な対応が必要となります。
なぜなら2025年10月1日にはさらなる改正施行が控えているからです。
本記事では、4月の法改正ポイント振り返りと、10月施行に向けた準備について解説いたします。
就業規則の全面改定は待ったなし!今すぐ全社的な対策を
2025年の育児・介護休業法改正では、比較的大きく変更がありました。
特に、以下の点は就業規則の改正や企業の対応に直接的な影響を及ぼす可能性があります。
- 【4月施行済】残業免除の対象拡大(小学校就学前まで)
- 【4月施行済】子の看護休暇の拡充(小学校3年生まで・取得事由も拡大)
- 【4月施行済】介護離職防止策の強化(個別周知・相談体制の義務化)
- 【10月施行】3歳以上の子を持つ従業員への両立支援策(2つ以上の制度導入義務)
もし、2025年4月施行分に未対応であれば、早急に就業規則の改定などの対応が必要です。10月の改正も目前である今、両方の改正内容をまとめて、直ちに対策を講じることが経営上の急務と言えます。
なぜ今、育児・介護休業法の改正が続くのか?
今回の法改正の背景には、深刻化する少子高齢化と、それに伴う労働力人口の減少があります。共働き世帯が当たり前となり、また、家族の介護を担う従業員も増加する中で、仕事と家庭の両立支援は、もはや福利厚生の一環ではなく、企業の持続的成長に不可欠な「経営戦略」となっています。
従業員が育児や介護を理由に離職することなく、安心して働き続けられる環境を整えることは、人材の確保・定着に直結します。法改正を「コスト」と捉えるのではなく、従業員エンゲージメントを高め、多様な人材が活躍できる魅力的な職場を作るための「投資」と捉える視点が重要です。
【対応必須】2025年4月1日施行済み!見直すべき5つのポイント
2025年4月1日に施行された、既に対応が完了していなければならない改正点です。自社の就業規則と運用が対応できているか、改めてご確認ください。
1. 所定外労働の制限(残業免除)対象者の拡大
これまで「3歳に満たない子」を養育する従業員が対象だった残業免除が、「小学校就学前の子」を養育する従業員まで拡大されました。
- 企業の対応:
- 就業規則(育児・介護休業規程)の関連規定が「小学校就学前」に改定されているか確認してください。
- 対象者の増加を見込み、特定の従業員に依存しない業務体制の構築が急務です。
2. 子の看護休暇制度の見直し
子の看護休暇制度が大幅に拡充されています。
- 対象となる子の範囲拡大: 「小学校就学前」から「小学校3年生修了まで」に引き上げ。
- 取得事由の拡大: 従来の病気・けがに加え、感染症に伴う学級閉鎖等や、子の入園式・卒園式といった行事への参加も取得可能に。
- 対象者の拡大: 労使協定で除外可能だった「勤続6か月未満の労働者」も対象に。
- 企業の対応:
- 労使協定の再締結や就業規則の改定が必要です。
- 休暇取得の申出に円滑に対応できる業務カバー体制の検討が必要です。
3. 育児のためのテレワーク導入(努力義務)
「3歳に満たない子」を養育する従業員から申出があった場合、テレワークを導入することが企業の努力義務となりました。
- 企業の対応:
- 努力義務ではありますが、導入しない場合は従業員に理由を説明できるよう準備が必要です。テレワーク規程の整備を検討しましょう。
4. 仕事と介護の両立支援制度の強化
介護離職ゼロを目指し、介護に直面した従業員を支援するための制度が強化されました。
- 個別周知・意向確認の義務化: 介護に直面した旨の申出があった従業員に対し、企業は関連制度を個別に知らせ、意向を確認することが義務化されました。
- 雇用環境の整備義務: 研修の実施や相談窓口の設置などが義務付けられています。
- 介護のためのテレワーク導入(努力義務): 要介護状態の家族を介護する従業員を対象に、テレワーク導入が努力義務化されました。
- 企業の対応:
- 制度案内資料や面談シートの準備、相談窓口担当者の設置・周知が完了しているか確認してください。
5. 育児休業取得状況の公表義務の拡大
従業員数1,000人超の企業に義務付けられていた男性の育児休業取得率等の公表義務が、従業員数300人超の企業まで拡大されました。
- 企業の対応:
- 対象企業は、自社の取得率を把握し、公表(自社ウェブサイトなど)の準備が必須です。
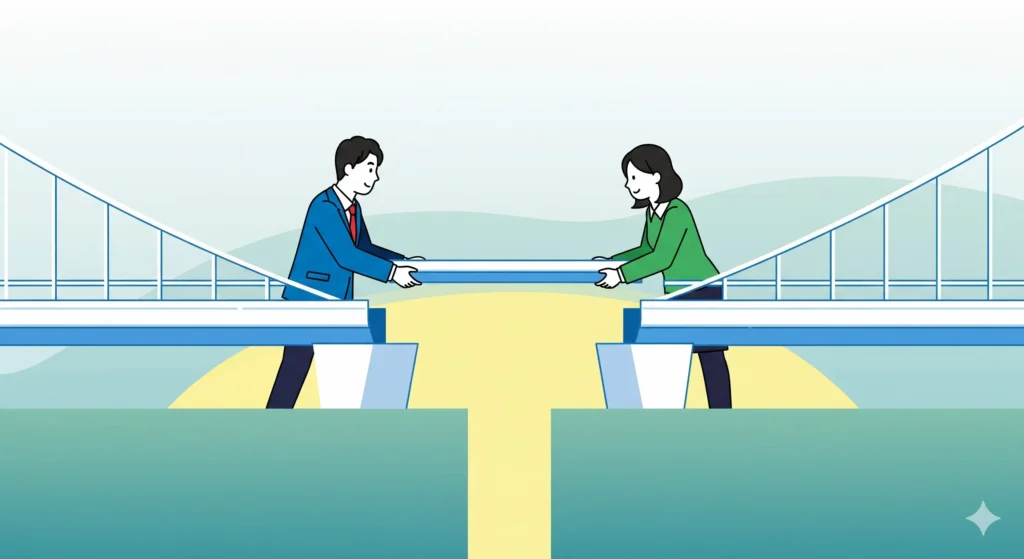
【目前に迫る!】2025年10月1日施行!育児両立支援の新たな義務
次に、10月1日に施行される改正点です。こちらはこれから準備が必要な項目です。
柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
「3歳から小学校就学前の子」を養育する従業員に対し、事業主は以下の措置の中から2つ以上を制度として導入し、従業員がその中から1つを選択して利用できるようにすることが義務化されます。
- 導入が義務付けられる選択肢
- 始業時刻等の変更(時差出勤、フレックスタイム制など)
- テレワーク
- 短時間勤務制度
- 新たな休暇の付与(子の行事参加や地域の活動への参加など、有給の休暇)
- その他(事業所内保育施設の設置運営など)
- 企業の対応:
- どの制度を導入するか、早急に検討・決定する必要があります。自社の業務実態や従業員のニーズを考慮し、最も効果的かつ導入可能な組み合わせを選択してください。
- 決定した制度について、就業規則に規定し、施行日までに従業員へ周知する必要があります。
- 従業員から利用の申出があった際の、申請手続きや運用フローを確立しておかなければなりません。
企業が”今すぐ”準備すべきことリスト
法改正への対応は、後回しにせず計画的に進めることが重要です。以下のリストを参考に、自社の進捗を緊急で確認してください。
- ☐ 【至急】4月施行分の改正内容が、就業規則に正しく反映されているか確認
- ☐ 【至急】10月施行分の「選択的措置義務」について、導入する2つ以上の制度を決定
- ☐ 4月分・10月分を反映させた就業規則(育児・介護休業規程)の改定案を作成
- ☐ 労使協定の確認・改定の要否検討
- ☐ 管理職への研修計画の策定(特に残業免除や各種休暇への理解促進)
- ☐ 全従業員への周知方法の検討(10月施行に向けた説明会の開催など)
- ☐ 各種様式(申出書、意向確認シートなど)の準備・見直し
- ☐ 育児・介護に関する相談窓口の再周知と機能確認
よくある質問(Q&A)
Q1. 2025年4月の法改正に未対応のままですが、罰則はありますか?
A1. 育児・介護休業法には直接的な罰則規定は多くありませんが、法違反に対しては、まず都道府県労働局から助言・指導・勧告が行われます。勧告に従わない場合は企業名が公表される可能性があります。また、従業員との間でトラブルが発生した場合、訴訟などに発展するリスクも高まります。何より企業の社会的信用を損なうため、一刻も早い対応が不可欠です。
Q2. 10月から始まる「選択的措置義務」ですが、中小企業で導入しやすい制度はどれですか?
A2. 企業の業種や規模によりますが、比較的導入しやすいのは「始業時刻等の変更(時差出勤)」や「新たな休暇の付与」です。テレワークや短時間勤務は、業務の切り出しや勤怠管理など、より詳細な検討が必要になります。まずは従業員のニーズを聞き取り、自社で無理なく運用できる制度から検討を始めるのが現実的です。
Q3. 介護に関する「個別周知・意向確認」は、具体的にどうすればよいのですか?
A3. 従業員本人から「親の介護が必要になった」といった申出があった際、あるいはそうした状況を企業が知った際に、人事担当者や直属の上司が面談の機会を設けるのが一般的です。「会社には介護休業や時短勤務、テレワークなどの制度がありますよ」と書面で示しながら説明し、「どの制度の利用を希望しますか?」あるいは「まずは情報収集したいですか?」といった形で従業員の意向を確認し、記録に残します。重要なのは、会社として支援する姿勢を示すことです。
まとめ
2025年9月現時点、育児・介護休業法の改正対応は待ったなしの状況です。特に、4月施行分にまだ対応できていない企業様は、法違反の状態にあるという危機意識を持ち、10月施行分と合わせた一体的な対策を大至急進める必要があります。
これらの法改正は、企業にとって負担だけではありません。従業員が安心して働き続けられる環境を整備することは、人材確保が困難な時代において、他社との大きな差別化要因となります。法改正を「義務」としてだけでなく、企業の持続的成長のための「機会」と捉え、前向きに取り組んでいきましょう。
ご不明な点や具体的な就業規則の改定については、ぜひ社労士事務所ウェルブルにご相談ください。貴社の状況に合わせた、最適な対応策をご提案させていただきます。