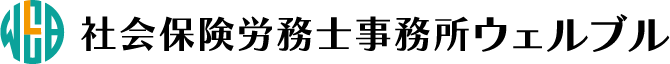相談主
相談主「起業してなんとか軌道に乗ってきたため、人を雇うことにしました。色々と手続きがあるそうですが、なにをすればいいのでしょうか。
また、しなかった場合は罰則などありますか?」
この度は、事業が軌道に乗り、初めて従業員を雇用されるとのこと、誠におめでとうございます。
さて、ご質問いただいた従業員雇用時の手続きについて、結論から申し上げます。
従業員を一人でも雇用した場合、事業主には、労働保険などへの加入が法律で義務付けられています。これらの手続きを怠ると、後から遡って保険料を請求されたり、悪質な場合には罰則が科されたりする重大なリスクがあります。
しかし、ご安心ください。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつ手順を踏んでいけば決して難しいものではありません。
この記事では、経験豊富な社会保険労務士として、初めて従業員を雇う経営者の皆様が最低限知っておくべき手続きの全体像、具体的な進め方、そして万が一手続きを怠った場合のリスクについて、分かりやすく丁寧に解説します。
なぜ労働保険・社会保険への加入が必須なのか?
そもそも、なぜこれらの保険への加入が法律で定められているのでしょうか。それは、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)が、従業員の生活を守るための国のセーフティネットだからです。
- 病気やケガ、出産をしたとき(健康保険)
- 業務中や通勤中にケガをしたとき(労災保険)
- 失業してしまったとき(雇用保険)
- 老後の生活資金(厚生年金保険)
これらの「もしも」の事態に備えるのが、各種保険の役割です。従業員が安心して働ける環境を整えることは、事業主の法的な義務であると同時に、従業員の定着率を高め、採用活動においても「信頼できる会社」というアピールに繋がる重要な要素となります。
初めて従業員を雇う際の「4つの保険」手続き完全ガイド
従業員を雇用する際に手続きが必要となる保険は、大きく分けて以下の4つです。
- 労災保険
- 雇用保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
1と2を合わせて「労働保険」、3と4を合わせて「社会保険」と呼びます。
手続きは、まず会社の事業所として労働保険と社会保険に加入し(適用)、その後、採用した従業員を被保険者として加入させる、という流れで進めます。
STEP1:労働保険の成立手続き
労働保険は、パートやアルバイトを含め従業員を一人でも雇った場合に加入義務が発生します。
① 労災保険:業務や通勤でのケガに備える
労災保険は、従業員が業務中や通勤中に起きた出来事が原因でケガや病気、死亡した場合に、治療費や休業中の賃金などを補償する制度です。
- 手続き先: 事業所の所在地を管轄する労働基準監督署
- 主な提出書類:
- 保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 提出期限: 従業員を雇った日の翌日から10日以内
② 雇用保険:失業時の生活を支える
雇用保険は、従業員が失業した場合に再就職を支援するための給付金(いわゆる失業手当)などを支給する制度です。
- 手続き先: 事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
- 主な提出書類:
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届(加入する従業員分)
- 提出期限: 事業所を設置した日(従業員を雇った日)の翌日から10日以内
STEP2:社会保険の新規適用手続き
社会保険は、法人の場合は事業主一人であっても加入義務があり、個人事業所の場合は常時5人以上の従業員を使用する場合に加入義務が発生します(一部業種を除く)。
③ 健康保険・④ 厚生年金保険:日々の健康と老後に備える
健康保険は、病気やケガをした際の医療費の自己負担を軽減する制度です。厚生年金保険は、老後に受け取る老齢年金のほか、障害年金や遺族年金などを保障する制度です。
- 手続き先: 事業所の所在地を管轄する年金事務所
- 主な提出書類:
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届(加入する従業員分)
- (従業員に扶養家族がいる場合)健康保険 被扶養者(異動)届
- 提出期限: 事業所を設立した日や従業員を雇用した日など、加入義務が発生した事実があった日から5日以内と、非常にタイトなので注意が必要です。
【事例で解説】Webデザイン会社A社のケース
創業3年目で順調にクライアントが増えてきたWebデザイン会社A社のB社長。
これまで一人で業務をこなしてきましたが、事業拡大のため、初めて正社員のデザイナーCさんを採用することにしました。
B社長は喜びと同時に、「手続きは何をすればいいんだ…?」と不安に。そこで、本記事を参考に必要な手続きをリストアップしました。
- まず労働基準監督署へ
- Cさんを雇った日の翌日から10日以内に「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出。
- 次にハローワークへ
- 同じく10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」とCさんの「雇用保険被保険者資格取得届」を提出。
- 最後に年金事務所へ
- 法人であるA社は、事実発生から5日以内に「新規適用届」とCさんの「被保険者資格取得届」を提出。
期限を守って無事に手続きを完了させたB社長。従業員のCさんも、万が一の際に備えがあることで安心して業務に集中でき、結果として会社の成長に大きく貢献してくれました。B社長は「従業員を守る体制を整えることが、会社の信頼と成長に繋がるのだ」と実感したのでした。


もし手続きを怠ったら?知っておくべき罰則とリスク
冒頭で触れた通り、これらの手続きを怠ると以下の罰則が課される可能性があります。
遡及適用と追徴金・延滞金
行政機関の調査などで未加入が発覚した場合、最大で過去2年間に遡って保険料を一括で支払うよう命じられます。
金額が高額になるケースも少なくありません。さらに、本来納めるべき保険料に加えて、追徴金や延滞金が課されることもあります。
法律による罰則
悪質なケースと判断されると、法律に基づく罰則が科される可能性があります。
- 健康保険法・厚生年金保険法: 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 雇用保険法: 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
従業員との信頼関係の崩壊
最も避けたいのが、従業員とのトラブルです。
例えば、業務中に従業員が大ケガをしたにもかかわらず、労災保険に未加入だった場合、治療費や休業補償は全額会社の負担となります。
また、失業手当がもらえない、年金の受給額が減るといった不利益は、従業員の会社に対する不信感に直結し、損害賠償請求などの重大なトラブルに発展しかねません。
よくある質問(Q&A)
Q1. パートやアルバイトでも手続きは必要ですか?
A1. はい、必要です。パートやアルバイトであっても、条件を満たせば労働保険・社会保険への加入は義務となります。
- 労災保険: 雇用形態にかかわらず、全ての従業員が対象です。
- 雇用保険:
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険):
- 正社員の週の所定労働時間および月の所定労働日数の4分の3以上働く場合。
- 上記に満たなくても、以下の要件を全て満たす場合は加入対象となります(※従業員数51人以上の企業の場合。2024年10月以降の制度)。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生でない
Q2. 役員だけでも社会保険に入る必要はありますか?
A2. はい、原則として加入義務があります。 法人を設立し、代表取締役や常勤の役員として会社から役員報酬を受け取っている場合は、たとえ従業員がいなくても社会保険の加入対象となります。ただし、非常勤であったり、報酬が極めて低額である場合など、加入対象外となるケースもありますので、詳しくは年金事務所に相談いただくか、弊所にご依頼ください。
Q3. 手続きが複雑でよく分かりません。どこに相談すればいいですか?
A3. ご安心ください。ご自身での手続きが不安な場合は、専門家にご相談いただくのが最も確実です。
必要書類の作成から提出代行まで、トータルでサポートいたします。ぜひ社会保険労務士事務所ウェルブルまでご相談ください。
まとめ
初めて従業員を雇う際の手続きは、一見すると煩雑で面倒に感じられるかもしれません。
しかし、これらは従業員が安心して能力を発揮し、会社が健全に成長していくための「土台」となる、非常に重要な手続きです。
手続きを怠ることによる金銭的、法的なリスクは計り知れません。何より、従業員との信頼関係を損なうことは、会社の将来にとって大きな損失となります。
この記事が、あなたの会社の輝かしい第一歩の一助となれば幸いです。もし少しでも不安な点や不明な点がございましたら、決して一人で抱え込まず、社会保険労務士事務所ウェルブルまでご相談ください。皆様の会社の健全な発展をサポートいたします。