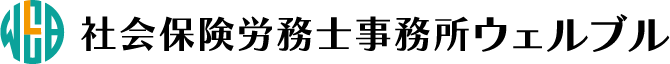「従業員の給与計算、毎月のことだから何となくルーティンでこなしている…」
中小企業の経営者様や人事担当者様の中には、このような方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、その「なんとなく」続けている給与計算には、会社の存続を揺るかしかねない重大なリスクが潜んでいる可能性があります。
給与計算は、単なる電卓を叩く作業ではありません。労働基準法、社会保険、税法など、多岐にわたる専門知識が求められる、非常に複雑で重要な経営業務です。たった一つの間違いが、追徴課税や未払い賃金の請求、そして何より大切な従業員との信頼関係の失墜につながることも少なくありません。
本記事では、経験豊富な社会保険労務士の視点から、給与計算に潜む具体的なリスクとその対策について、事例を交えながら分かりやすく解説します。毎月の業務に潜む危険性を正しく理解し、健全な会社経営にお役立てください。
なぜ給与計算はこんなにも難しいのか?
毎月繰り返される業務であるにもかかわらず、なぜ給与計算はこれほどまでに間違いやすく、難しいのでしょうか。その理由は主に3つあります。
1. 複雑に絡み合う法律の知識が必要
給与計算は、主に以下の法律が複雑に関係しています。
- 労働基準法: 時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働に対する割増賃金の計算ルールが定められています。
- 最低賃金法: 従業員の給与が、国や都道府県が定める最低賃金を下回っていないかを確認する必要があります。
- 健康保険法・厚生年金保険法: 従業員の給与額に応じて社会保険料を算出し、給与から控除します。
- 雇用保険法: 業種によって異なる保険料率を元に、雇用保険料を計算します。
- 所得税法: 従業員の扶養家族の状況などに応じて、源泉所得税を計算し、納付する必要があります。
これらの法律をすべて正確に理解し、運用するのは容易ではありません。
2. 頻繁に行われる法改正への対応
社会保険料率や最低賃金額、税制などは、毎年あるいは不定期に改正されます。
例えば、近年では育児・介護休業法の改正に伴い、社会保険料の免除要件が変更されるなど、常に最新の情報をキャッチアップし、計算方法を更新し続ける必要があります。この情報収集を怠ると、気づかないうちに法律違反を犯してしまうリスクがあります。
出典:厚生労働省 育児・介護休業法改正ポイントのご案内(2025年)
3. 従業員ごとに異なる労働条件
従業員一人ひとり、給与体系、労働時間、手当、扶養家族の有無などが異なります。
正社員、契約社員、パート・アルバイトといった雇用形態の違いによっても、社会保険の加入義務や割増賃金の計算基礎が変わってきます。これらの個別事情をすべて正確に把握し、一人ひとり間違いなく計算を行うには、細心の注意が必要です。
【事例で解説】給与計算に潜む5つの重大リスク
では、実際に給与計算を誤ると、どのような事態に発展するのでしょうか。
ここでは、中小企業で起こりがちな5つのリスクを具体的な事例とともにご紹介します。
リスク1:残業代の未払い(労働基準法違反)
【A社のケース】 IT企業のA社では、営業職の社員に「営業手当」として月額3万円を固定残業代として支給していました。
しかし、就業規則や雇用契約書に「営業手当が●時間分の時間外手当に相当する」という明確な定めがなかったため、退職した従業員から「営業手当は残業代とは認められない。過去2年分の未払い残業代を支払ってほしい」と請求されてしまいました。
労働基準監督署の調査も入り、結果的に多額の未払い残業代と遅延損害金の支払いを命じられました。
- ポイント: 固定残業代(みなし残業代)制度を導入する場合は、その金額が何時間分の残業代に相当するのかを明確に定め、実際の残業時間がそれを超えた場合は差額を支払う必要があります。
リスク2:社会保険料の計算ミスによる追徴
【B社のケース】 製造業を営むB社では、ある従業員が春に大幅な昇給をしました。
本来であれば、昇給後の3ヶ月間の給与の平均額を基に社会保険料の等級(標準報酬月額)を見直す「随時改定」の手続きが必要でした。
しかし、担当者がその手続きを失念。1年後の年金事務所の調査で発覚し、会社負担分と従業員負担分を合わせた1年分の差額、さらに延滞金を一括で納付するよう指導されました。
従業員からも追加で保険料を徴収せざるを得ず、不信感を与えてしまいました。
- ポイント: 昇給や降給により給与額が大きく変動した際は、「随時改定」の手続きを忘れないようにしましょう。 出典:日本年金機構 標準報酬月額・標準賞与額とは?
リスク3:税金の徴収漏れ(源泉所得税・住民税)
【C社のケース】 サービス業のC社では、電車で通勤する従業員に月額16万円の通勤手当を支給していました。
担当者は通勤手当は全額非課税だと認識していましたが、所得税法上の非課税限度額は月15万円までです。
税務調査でこの点を指摘され、限度額を超えた1万円部分に対する源泉所得税の徴収漏れが発覚。過去に遡って、不納付加算税や延滞税を含めた税金を納めることになりました。
- ポイント: 通勤手当をはじめ、各種手当には課税対象となるものと非課税となるものがあります。その区分を正確に理解しておくことが重要です。 出典:国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
リスク4:気づかぬうちに最低賃金割れ
【D社のケース】 飲食店を経営するD社では、時給1,100円でアルバイトを雇用していました。地域の最低賃金は1,080円だったため、問題ないと考えていました。しかし、研修期間中は「研修時給」として時給1,050円を支払っていたことが発覚。これは最低賃金法違反にあたり、労働基準監督署から是正勧告を受け、差額を支払うことになりました。
- ポイント: 最低賃金は毎年改定される可能性があります。常に最新の金額を確認し、それを下回らないように注意が必要です。月給制の従業員の場合も、時給に換算して最低賃金をクリアしているか確認しましょう。 出典:厚生労働省 確かめよう最低賃金
リスク5:従業員との信頼関係の悪化
これまで挙げたリスクはすべて、最終的にこのリスクにつながります。
給与は、従業員の生活を支える最も重要な基盤です。その計算に間違いがあったり、給与明細の内容が不透明だったりすると、従業員は会社に対して強い不信感を抱きます。「この会社は大丈夫なのだろうか…」と不安を感じ、優秀な人材のモチベーション低下や離職につながることも少なくありません。
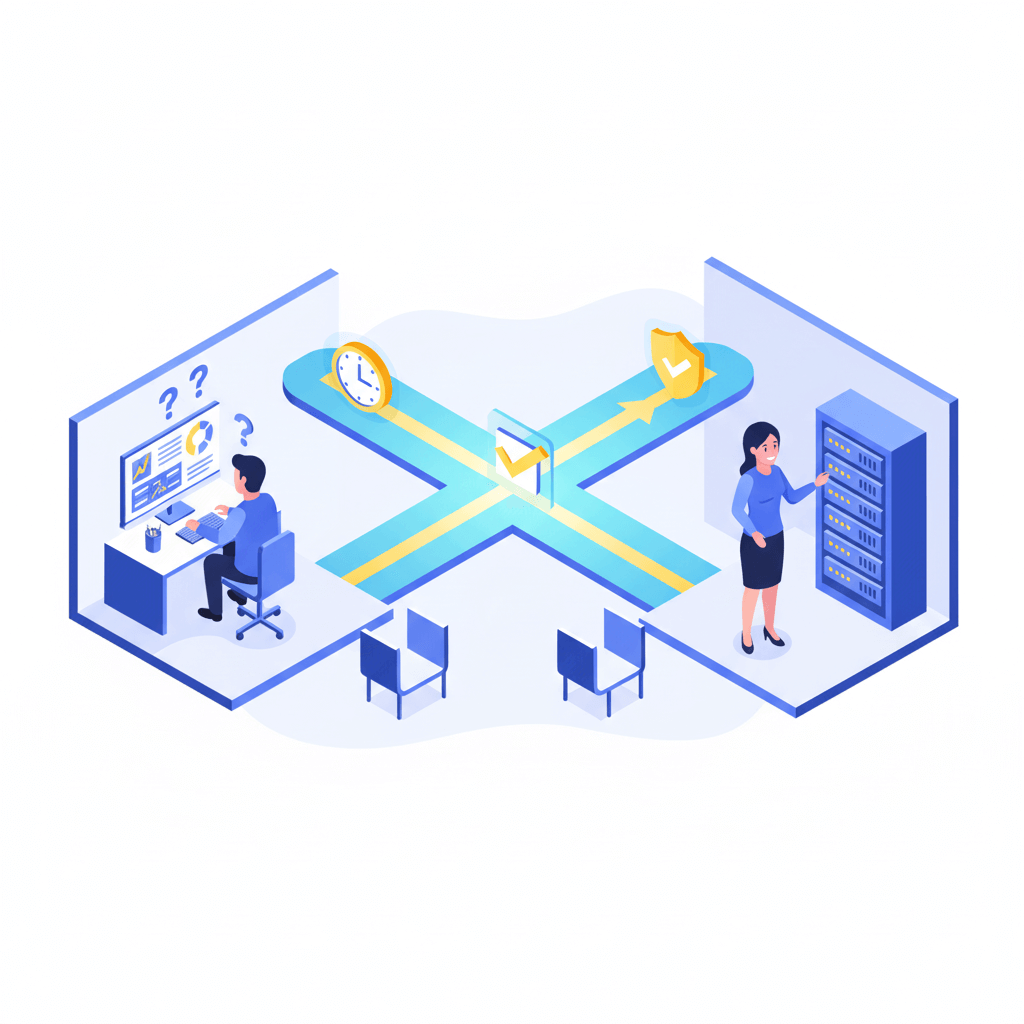
今すぐできる!給与計算のリスクを回避する3つの対策
では、これらのリスクを回避し、正確な給与計算を行うためにはどうすればよいのでしょうか。
1. 正確な勤怠管理の徹底
すべての計算の基礎となるのが、正確な労働時間の把握です。
タイムカード、ICカード、勤怠管理システムなどを活用し、1分単位で客観的な記録を残すことが重要です。「何時から何時まで働いたか」を正確に管理することが、正しい残業代計算の第一歩です。
2. ダブルチェック体制の構築
どれだけ注意していても、一人の人間が作業する以上、ミスは起こり得ます。
必ず計算担当者とは別の人がチェックする体制を構築しましょう。経営者自身が最終確認を行う、あるいは担当者間で相互にチェックするなど、社内の実情に合わせたルール作りが不可欠です。
3. 専門家への相談・アウトソーシングの検討
「自社だけでは不安だ」「法改正のキャッチアップが追いつかない」と感じる場合は、専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。 給与計算業務をアウトソーシング(外部委託)すれば、以下のようなメリットがあります。
- 法改正への自動対応: 常に最新の法律に基づいた正確な計算が保証されます。
- 担当者の負担軽減: 複雑な業務から解放され、本来のコア業務に集中できます。
- 客観性の担保: 専門家が第三者の視点で計算することで、公平性と正確性が高まります。
- 経営リスクの低減: 未払いや追徴課税といったリスクを未然に防ぎ、経営の安定化に繋がります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 給与計算で特に間違いやすいポイントは何ですか?
A1. 特に間違いが多いのは以下の3点です。
- 残業代の計算: 割増率(時間外25%増、休日35%増、深夜25%増)の適用漏れや、計算の基礎となる賃金に含めるべき手当(役職手当など)を除外してしまうケース。
- 社会保険料の控除: 入社・退社時の日割り計算の要否や、賞与支払時の保険料計算、育児休業中の保険料免除の適用ミスなど。
- 扶養人数の変動: 従業員の子どもが就職したり、配偶者の収入が増えたりして扶養から外れたにもかかわらず、変更手続きが漏れて源泉所得税額が誤ったままになるケース。
Q2. 給与計算を間違えた場合、どのような罰則がありますか?
A2. 間違いの内容によって異なりますが、主に以下のようなペナルティが課される可能性があります。
- 労働基準法違反(賃金未払いなど): 30万円以下の罰金や、悪質な場合は6ヶ月以下の懲役。付加金(未払い額と同額)の支払いを命じられることもあります。
- 税金の納付漏れ: 本来の税額に加え、不納付加算税(10%)や延滞税が課されます。
- 社会保険料の納付漏れ: 本来の保険料に加え、延滞金が課されます。
Q3. 給与計算をアウトソーシングするメリットとデメリットを教えてください。
A3. メリットは、「正確性の向上」「担当者の負担軽減」「法改正への自動対応」「経営リスクの低減」です。
一方、デメリットとしては「外部委託コストの発生」「社内に給与計算ノウハウが蓄積されにくい」といった点が挙げられます。しかし、万が一のリスク発生時の損失(追徴課税や未払い賃金)を考えれば、専門家への委託コストは有効な投資と言える場合がほとんどです。
まとめ
給与計算は、会社の信用と従業員の生活を守るための、極めて重要な業務です。毎月のルーティンワークとして「なんとなく」処理するのではなく、その背後にある法律やリスクを正しく認識し、正確な業務遂行を徹底することが、企業の持続的な成長には不可欠です。
自社での対応に少しでも不安を感じたり、担当者の負担が大きくなっていたりする場合は、ぜひ一度、私たち社会保険労務士にご相談ください。専門家の知見を活用することが、未来のトラブルを防ぎ、経営者様が安心して事業に専念できる環境を整えるための、最も確実な一歩となります。