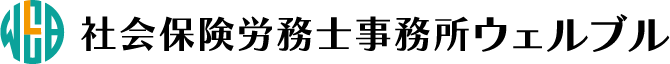「毎月の給与計算、正直なところ負担が大きい…」
「法改正のたびに情報を追いかけるのが大変…」
「うちは人数も少ないし、外部に頼むほどではないかな?」
日々、多くの経営者様からこのようなご相談を受けます。
特に、リソースが限られる中小企業にとって、給与計算や社会保険手続きは、正確性が求められる一方で、直接的な利益を生み出さないノンコア業務です。
結論から申し上げます。多くの中小企業にとって、給与計算や社会保険手続きは外部の専門家へ委託(アウトソーシング)する方が、隠れたコストの削減やリスク回避に繋がり、結果的に経営の安定化と成長に貢献します。
この記事では、なぜ外部委託が有効な選択肢となり得るのか、内製化に伴う「隠れコスト」と、アウトソーシングがもたらす具体的なメリットを、事例を交えながら徹底的に比較・解説します。
給与計算・社保手続きを内製化する際に見落としがちな「隠れコスト」
「外部委託は費用がかかるから、自社でやった方が安い」と考えるのは自然なことです。しかし、内製化には人件費以外にも、目に見えにくい様々な「隠れコスト」が存在します。
人件費だけではない!担当者の「時間」という最大のコスト
最も大きなコストは、担当者の「業務時間」です。仮に月給30万円の担当者が、業務時間全体の20%を給与計算・社保手続きに費やしているとすれば、毎月6万円の人件費がこの業務に充てられている計算になります。
- 勤怠データの集計
- 残業代や各種手当の計算
- 社会保険料・雇用保険料・税金の計算
- 給与明細書の作成・配布
- 従業員からの問い合わせ対応
- 入退社に伴う資格取得・喪失手続き
これらの作業時間は、本来であれば採用活動、人材育成、社内制度の整備といった、企業の成長に直結する戦略的な業務に使えるはずの時間です。
専門知識の習得と維持のコスト
労働関連法規や社会保険制度は、毎年のように改正が行われます。
- 社会保険料率・雇用保険料率の変更
- 所得税・住民税の定額減税などの税制改正
- 育児・介護休業法の改正
これらの変更に正確に対応するためには、担当者がセミナーに参加したり、専門書を読んだりして、常に最新の知識を学び続ける必要があります。この学習時間や研修費用も、見過ごせないコストと言えるでしょう。
システム・ツール利用料と維持管理コスト
給与計算ソフトの導入費用や月額利用料もコストです。
また、給与明細書や各種届出書類の印刷にかかる紙代、インク代、それらを保管するためのファイルやキャビネット代、さらには情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策費用も含まれます。
ミスや遅延が引き起こす「リスク」という名のコスト
もし計算ミスや手続きの遅延が発生した場合、その影響は金銭的な損失だけにとどまりません。
- 従業員との信頼関係の損失: 給与の計算ミスは、従業員の会社に対する不信感に直結します。
- 法的リスク・追徴課税: 労働基準法違反による是正勧告や、社会保険・税金の納付漏れによる延滞金・追徴課税のリスクがあります。
- 行政手続きの遅延: 入社した従業員の保険証発行が遅れるなど、従業員に直接的な不利益を与えてしまう可能性もあります。
これらの「隠れコスト」や「リスク」を総合的に考慮すると、内製化が必ずしも「安上がり」とは言えないことがお分かりいただけるかと思います。

給与計算・社保手続きを外部委託する4つの大きなメリット
では、アウトソーシングにはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは代表的な4つのメリットをご紹介します。
1. トータルコストの削減と明確化
前述の「隠れコスト」を含めて考えると、専門家への委託費用が結果的に安くなるケースは少なくありません。委託費用は毎月定額であることが多く、コスト管理が容易になる点も大きなメリットです。担当者の急な退職に伴う採用・教育コストなども発生しません。
2. 専門性の確保と法改正への迅速な対応
社会保険労務士は、労働法規・社会保険制度の専門家です。常に最新の法改正情報を把握しており、正確な手続きを保証します。
- 正確な給与計算: 複雑な残業代計算や保険料控除もミスなく行います。
- 確実な行政手続き: 毎年更新される保険料率にも確実に対応します。[出典:日本年金機構 令和2年度以降の協会けんぽの保険料率] のように、専門家は常に最新の公式情報を基に業務を行います。
- リスク回避: 法令遵守(コンプライアンス)が徹底されるため、行政調査や労務トラブルのリスクを大幅に軽減できます。
3. 経営資源のコア業務への集中
アウトソーシングによって最も大きな恩恵を受けるのが、経営資源の最適化です。人事担当者は定型的な事務作業から解放され、採用、教育、評価制度の構築、従業員のエンゲージメント向上といった、会社の未来を創る「コア業務」に集中できるようになります。これは、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。
4. 属人化の防止とセキュリティ向上
「給与計算は〇〇さんしか分からない」という状況は、非常に大きな経営リスクです。その担当者が休職・退職してしまえば、業務が完全にストップしてしまいます。アウトソーシングは、この属人化リスクを根本から解消します。 また、専門事務所はマイナンバーなどの個人情報を扱うための高度なセキュリティ体制を構築しており、自社で管理するよりも情報漏洩リスクを低減できるという側面もあります。
【具体例で比較】従業員30名の中小企業のケーススタディ
ここで、具体的な事例を用いて内製と外部委託のコストを比較してみましょう。
【株式会社A社の状況】
- 従業員数: 30名
- 担当者: 総務・人事担当者1名(月給32万円)
- 現状: 担当者が給与計算・社保手続きに毎月約30時間(業務全体の約20%)を費やしている。給与計算ソフトの月額利用料が1万円。
<内製の場合の月額コスト>
- 人件費: 320,000円 × 20% = 64,000円
- 会社負担分社会保険料:45,000円× 20% = 9,000円
- システム利用料: 15,000円
- その他(研修費・雑費など): 約5,000円(年間6万円と仮定)
合計: 約93,000円 / 月 これに加えて、法改正対応の学習時間やミスのリスクといった「見えないコスト」が上乗せされます。
<外部委託(社労士事務所)の場合の月額コスト>
- 委託料金(顧問契約あり):
- 労務相談+社保手続‥44,000円
- 給与計算‥ 基本料金12,000円+人数(計算対象−5)✕900円=34,500円
- ※料金は弊所の例。
合計: 78,500円 / 月
このケーススタディでは、外部委託する方が月々14,500円、年間で174,000円の直接的なコスト削減に繋がりますし、法改正時や労務トラブル時の相談、助成金の情報提供や申請代行も依頼することが可能になります。
さらに重要なのは、担当者が確保できた月間30時間です。この時間を採用活動や社員面談に充てることで、人材の定着率向上や組織力強化といった、金額以上の価値を生み出すことができるのです。
よくある質問(Q&A)
Q1. アウトソーシングすると、自社に給与計算のノウハウが蓄積されないのが不安です。
A1. 確かに、計算実務のノウハウは蓄積されにくいかもしれません。しかし、アウトソーシングは単なる「丸投げ」ではありません。専門家と連携することで、自社の労務管理上の課題が明確になったり、より良い制度設計に関するアドバイスを受けられたりと、より高度で戦略的なノウハウを吸収する機会と捉えることができます。重要なのは、計算方法を知ることよりも、その結果をどう経営に活かすかです。
Q2. どのくらいの規模の会社から外部委託を検討すべきですか?
A2. 従業員数に明確な基準はありません。たとえ従業員が5名であっても、社長自身が給与計算に時間を取られて本業に集中できないのであれば、それは立派な検討理由になります。一つの目安として、「担当者の負担が目に見えて増えてきた」「初めて育休や介護休業を取得する従業員が出た」「法改正への対応に不安を感じ始めた」といったタイミングで、一度専門家への相談を検討してみることをお勧めします。
Q3. 委託先の社会保険労務士はどのように選べばよいですか?
A3. 以下のポイントを参考に、複数の事務所を比較検討すると良いでしょう。
- 実績と専門性: 自社の業種に関する知識や実績が豊富か。
- 料金体系の明確さ: どこまでの業務が料金に含まれているか、追加料金の有無などが明確か。
- コミュニケーションの円滑さ: 相談しやすいか、レスポンスは迅速か。担当者との相性も重要です。
- 対応範囲の広さ: 給与計算だけでなく、助成金の申請や就業規則の作成、労務相談など、幅広く対応してくれるか。
- セキュリティ対策: 個人情報を守るための体制が整っているか。
まとめ
給与計算や社会保険手続きのアウトソーシングは、単なる「コスト削減策」ではなく、リスクを回避し、限りある経営資源を会社の成長エンジンである「コア業務」に集中させるための戦略的な経営判断です。
- 内製化には、人件費以外の「隠れコスト」や「リスク」が潜んでいる。
- 外部委託は、専門性の確保と法改正への対応を可能にし、担当者をコア業務に専念させる。
- 多くの場合、トータルコストで見ると外部委託の方が有利になる。
貴社の貴重な人材と時間を、ノンコア業務から解放してみませんか。まずは自社の現状を把握し、専門家である社会保険労務士に相談してみることから始めてみてはいかがでしょうか。私たちが、貴社の経営を力強くサポートいたします。