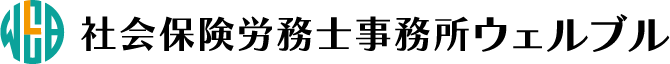「専門家に頼むと高そう…」
「うちは小さい会社だからまだ早いかな」
社会保険労務士(社労士)への業務委託を検討する際、多くの経営者様や人事担当者様がコストに関する不安を抱えていらっしゃいます。しかし、社労士への委託は、目先の費用を上回る多大なメリットをもたらす、極めて合理的な経営判断です。
本記事では、経験豊富な社会保険労務士の視点から、社労士に委託した場合の費用対効果を具体的な金額でシミュレーションし、人件費の削減、助成金の活用、そして見過ごされがちな「隠れコスト」の削減といった、企業成長に直結するメリットを詳しく解説します。
人事担当者1名の雇用 vs 社労士への委託 コスト比較
まず、最も分かりやすいコスト削減効果を比較してみましょう。人事労務の担当者を1名雇用する場合と、社労士にアウトソーシングする場合の年間コストをシミュレーションします。
【ケーススタディ】従業員30名の中小企業A社の場合
- 人事担当者を1名雇用した場合
- 給与:月額30万円(年収360万円)
- 社会保険料(会社負担分):約54万円(年収の約15%と仮定)
- 賞与:年2回(計60万円)
- 採用コスト(求人広告費など):約40万円
- その他(交通費、福利厚生費、PC等備品代):約30万円
- 合計:年間 約544万円
- 社労士に委託した場合(顧問契約+給与計算)
- 顧問契約料:月額4.4万円
- 給与計算料:月額3.4万円(基本料金+従業員単価)
- 合計:年間 約94万円(ウェルブルにご依頼いただいた場合の例)
| 比較項目 | 人事担当者1名雇用 | 社労士へ委託 |
| 年間コスト | 約544万円 | 約94万円 |
| 差額 | 年間 約450万円の削減効果 |
この比較から分かるように、社労士に委託することで、単純計算でも年間400万円以上の直接的なコスト削減が期待できます。 もちろん、担当者の採用や教育にかかる時間的コスト、退職リスクなども考慮すると、その差はさらに大きくなります。
経営者様や既存の従業員様が本来のコア業務に集中できる時間を確保できるという、数字には表れにくい生産性向上のメリットも計り知れません。
知らないと損をする「助成金」の活用という大きなリターン
社労士に委託するメリットは、コスト削減だけではありません。
むしろ、「攻めの労務管理」として大きなリターンが期待できるのが、助成金の活用です。
国や地方自治体は、雇用の安定や労働環境の改善、人材育成などに取り組む企業を支援するために、多種多様な助成金制度を用意しています。
しかし、その多くは制度が複雑で、申請書類の作成も煩雑なため、専門知識がなければ活用が難しいのが実情です。
また、助成金は労働関連法を満たしている企業が受給できますが、知識がない状態で助成金を満たすような労働条件や体制を整えるのは難しいです。
【事例】B社(ITサービス業・従業員15名)のケース
契約社員として半年間勤務していた優秀なエンジニアを正社員に転換することを検討していました。顧問社労士に相談したところ、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の活用を提案されました。
- 社労士のサポート内容
- キャリアアップ計画書の作成・提出
- 就業規則の改定(転換制度の明記)
- 転換後の労働条件の整備
- 支給申請書の作成・提出
- 得られたリターン
- 助成金受給額:40万円 (有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合の金額。金額は変更される可能性があります)
- 社労士への報酬(成功報酬):約6万円(受給額の15%と仮定)
- 差し引きリターン:34万円
B社は、社労士に依頼することで、実質的に34万円以上の資金を得ながら、優秀な人材の定着を実現しました。これはほんの一例であり、他にも業務改善助成金や両立支援等助成金など、活用できる助成金は数多く存在します。
出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金 ※助成金の詳細や金額は年度によって改定されます。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

最大のメリットは「労務リスク」の回避
見落とされがちですが、社労士に委託する最大のメリットは、「労務リスク」を未然に防ぐことにあると言っても過言ではありません。
サービス残業の常態化、不適切な解雇、ハラスメント問題など、労務トラブルは一度発生すると、企業の存続を揺るかしかねない大きな経営リスクとなります。
- 未払い残業代請求: 従業員1人から過去2年分(労働基準法の改正により将来的には5年に延長される可能性があります)の未払い残業代を請求され、数百万円の支払いを命じられるケースは少なくありません。
- 不当解雇訴訟: 裁判に発展した場合、解決までに長い時間と多額の弁護士費用がかかります。解雇が無効と判断されれば、解雇期間中の給与(バックペイ)の支払いも発生し、その金額は1,000万円を超えることもあります。
- 企業の信用の失墜: 労務トラブルは、SNSなどを通じて瞬く間に拡散され、企業のブランドイメージや採用活動に深刻なダメージを与えます。
社労士は労働法の専門家として、最新の法改正に対応した就業規則の整備や適切な労働時間管理、労使トラブルを未然に防ぐためのアドバイスを行います。
顧問料は将来発生するかもしれない数百万円、数千万円の損失を防ぐための「保険」と考えることができます。これは、経営における賢明なリスクマネジメントといえるのではないでしょうか。
まとめ:社労士への委託は未来への戦略的投資
改めて結論を申し上げます。社労士への業務委託は、単なるコスト削減や業務のアウトソーシングではありません。
- 直接的なコスト削減: 人事担当者の雇用に比べて、年間数百万単位のコストを削減できる。
- 積極的な利益創出: 活用が難しい助成金を活用し、数十万~数百万円のリターンを得られる。
- 潜在的リスクの回避: 労務トラブルという経営上の時限爆弾を未然に防ぎ、数百万~数千万円の損失を回避する。
- 生産性の向上: 経営者や従業員がコア業務に集中できる環境を創出し、企業全体の成長を加速させる。
これらのメリットを総合的に考慮すれば、社労士への委託費用は「コスト」ではなく、企業の持続的な成長を実現するための「戦略的投資」であるといえます。
複雑化する労務管理の課題を専門家に任せ、経営者様は安心して事業の成長に専念する。そのパートナーとして、ぜひ社会保険労務士の活用をご検討ください。
よくある質問(Q&A)
Q1. 顧問契約にはどのような種類がありますか?費用はどのくらいかかりますか?
A1. 顧問契約は、大きく分けて2種類あります。
- 労務相談顧問: 労務に関する相談や法改正情報の提供、助言がメインです。
- 手続・給与計算顧問: 相談業務に加え、社会保険・労働保険の手続き代行や給与計算まで業務代行いたします。
費用は従業員数等で変動しますが、基準をこちらのページに記載しています。
ヒアリングの結果(手続きの多少等)により、こちらに記載している金額から変動することがございますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
Q2. 小さな会社でも社労士に依頼するメリットはありますか?
A2. むしろ、社長自身が人事労務を兼ねていることが多い中小企業やスタートアップ企業こそ、社労士に依頼するメリットは大きいと言えます。煩雑な手続きから解放され、経営という本来の業務に集中できます。
また、会社設立時から適切な労務管理体制を構築しておくことで、将来のトラブルを未然に防ぎ、健全な成長基盤を築くことができます。