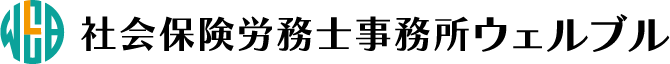「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉を耳にする機会が増えましたが、「うちのような中小企業には関係ない」「何から手をつけていいか分からない」と感じている経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、労務管理の領域におけるDX「労務DX」は、実は中小企業にこそ大きな経営メリットをもたらす施策なのです。
本記事では、労務DXが初めての方でも安心して取り組めるよう、その基本から具体的な進め方、そして成功の秘訣までを、社会保険労務士の視点から分かりやすく解説します。
結論から言えば、労務DXはスモールスタートが可能であり、正しく進めれば必ず企業の成長を後押しする力強い味方となります。
なぜ今、中小企業に「労務DX」が必要なのか?
「これまでも手作業で何とかなってきたのに、なぜ今さらシステムを導入する必要があるのか?」そう思われるかもしれません。しかし、企業を取り巻く環境は大きく変化しており、従来のやり方では対応が困難な課題が増えています。
1. 待ったなしの法改正への対応
近年、労働関連の法改正が頻繁に行われています。記憶に新しい「働き方改革関連法」や、2024年から本格化した電子帳簿保存法の改正などがその代表例です。
特に、社会保険・労働保険に関する一部手続きは、2020年4月から大企業を対象に電子申請が義務化されました。この流れは今後、中小企業にも及ぶ可能性が十分に考えられます。法改正のたびに手作業で対応するのは非常に煩雑であり、DX化によるスムーズな対応が不可欠です。
出典:e-Govからのお知らせ 2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます
2. 深刻化する人手不足と生産性向上
少子高齢化に伴い、多くの中小企業が人手不足という深刻な課題に直面しています。限られた人材で事業を継続・発展させていくためには、従業員一人ひとりの生産性を向上させることが絶対条件です。 タイムカードの集計、給与計算、入退社手続きといった定型的な労務作業に多くの時間を費やしている場合、労務DXによってこれらの業務を自動化することで、担当者はより付加価値の高いコア業務に集中できるようになります。
3. 多様な働き方への柔軟な対応
リモートワークや時短勤務など、従業員の働き方は多様化しています。こうした新しい働き方を支える上で、紙ベースの勤怠管理や申請・承認プロセスは大きな障壁となります。 クラウド型の労務管理システムを導入すれば、従業員は場所を選ばずにスマートフォンやPCから打刻や各種申請ができ、管理者はリアルタイムで状況を把握できます。多様な働き方に対応できる環境は、優秀な人材の確保・定着にも繋がります。
労務DXがもたらす具体的なメリット
労務DXを導入することで、企業は具体的にどのような恩恵を受けられるのでしょうか。主なメリットを4つご紹介します。
- 圧倒的な業務効率化とコスト削減
- 手作業で行っていた給与計算や勤怠集計が自動化され、作業時間を大幅に削減できます。
- ペーパーレス化により、紙代、印刷代、保管スペースといった物理的なコストも削減されます。
- ヒューマンエラーの防止と正確性の向上
- 手入力や転記作業がなくなることで、計算ミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぎます。
- 法改正にもシステムが自動でアップデート対応するため、常に最新の法令に基づいた正確な労務管理が実現できます。
- 迅速な経営判断をサポート
- 勤怠データや人件費データをリアルタイムで可視化できます。
- これにより、残業時間の傾向分析や適正な人員配置の検討など、データに基づいた迅速かつ的確な経営判断が可能になります。
- 従業員満足度の向上
- スマートフォンで給与明細を確認できたり、各種申請がオンラインで完結したりと、従業員の利便性が向上します。
- 煩雑な事務手続きから解放されることは、従業員満足度の向上、ひいてはエンゲージメントの強化に貢献します。
【領域別】労務DXはどこから始めるべき?優先順位の考え方
「労務DXのメリットは分かったが、具体的にどの業務から手をつければ良いのか?」これは多くの経営者様が抱える悩みです。そこで、労務DXの対象領域を整理し、導入の優先順位の考え方について解説します。
優先順位は、以下の3つの軸で判断するのがお勧めです。
- 効果の実感しやすさ: 担当者だけでなく、全従業員がメリットを感じられるか?
- 業務インパクトの大きさ: 日常業務の中で、最も時間や手間を奪っている業務はどれか?
- 法対応などの緊急性: 法改正や社会的な要請への対応が急がれる業務はどれか?
これを踏まえ、代表的な4つの領域を見ていきましょう。
領域1:勤怠管理(推奨度:★★★★★)
- 特徴: 全従業員が毎日利用するため、DX化の効果を最も実感しやすい領域です。タイムカードの集計やExcelへの転記作業を自動化でき、人事担当者の工数を劇的に削減します。リモートワークや直行直帰など多様な働き方への対応も可能になります。
- こんな企業に最適:
- 紙のタイムカードやExcelで勤怠管理を行っている。
- 毎月の勤怠の締め作業に時間がかかっている。
- リモートワークの導入を検討している、または既に導入している。
領域2:給与明細の電子化(Web給与明細)(推奨度:★★★★☆)
- 特徴: 比較的、導入のハードルが低く、ペーパーレス化の第一歩として最適です。給与明細の印刷・封入・配布といった一連の作業とコスト(紙代、インク代、郵送費など)を完全にゼロにできます。従業員はスマホやPCでいつでも明細を確認でき、利便性が向上します。
- こんな企業に最適:
- 毎月、紙の給与明細を手渡しや郵送で配布している。
- 手軽に始められるペーパーレス化を探している。
- 印刷や配布のコスト・手間を削減したい。
領域3:給与計算(推奨度:★★★★☆)
- 特徴: 勤怠管理システムと連携させることで、効果が最大化する領域です。集計された勤怠データを元に、社会保険料や所得税などを自動で計算するため、ヒューマンエラーを撲滅できます。頻繁な保険料率の変更など、法改正にも自動で対応してくれるため安心です。
- こんな企業に最適:
- Excelや電卓で給与計算を行っており、ミスに不安がある。
- 勤怠管理と給与計算の二重入力の手間をなくしたい。
- 法改正への対応に不安や手間を感じている。
領域4:入退社・労務手続き(推奨度:★★★☆☆)
- 特徴: 従業員の入社や退社、扶養家族の変更、年末調整といった、発生頻度は低いものの手続きが煩雑な業務を効率化します。役所に提出する書類を自動で作成したり、電子申請(e-Gov連携)したりすることが可能です。
- こんな企業に最適:
- 従業員の入退社が頻繁に発生する。
- 年末調整の書類回収やチェックに毎年苦労している。
- 社会保険手続きのペーパーレス化、電子申請を進めたい。
まずは自社の状況を振り返り、「勤怠管理」や「給与明細の電子化」など、多くの従業員が関わり効果を実感しやすい領域からスモールスタートするのが成功への近道です。

失敗しないための労務DX導入5ステップ
では、具体的にどのように労務DXを進めていけば良いのでしょうか。失敗しないための5つのステップをご紹介します。
ステップ1:現状の課題を洗い出す
まずは、自社の労務管理における課題を具体的に洗い出しましょう。「何に」「誰が」「どれくらい」時間がかかっているのかを可視化することが重要です。
- (例)タイムカードの集計とExcelへの入力に、毎月10時間かかっている。
- (例)入社手続きの書類作成と役所への提出に、1人あたり半日かかっている。
- (例)従業員からの有給休暇の申請・承認が紙ベースで煩雑。
ステップ2:目的とゴールを明確にする
洗い出した課題の中から、最も解決したいことは何か、労務DXによって「どうなりたいか」という目的(ゴール)を明確に設定します。
- (例)勤怠管理にかかる時間を80%削減する。
- (例)給与計算のミスをゼロにする。
- (例)2ヶ月以内にペーパーレスでの年末調整を実現する。
ステップ3:目的に合ったツールを選定する
目的が明確になったら、それを実現できるツールを選びます。世の中には多くの労務DXツールがありますが、選定の際は以下のポイントをチェックしましょう。
- 機能: 自社の目的に合った機能が搭載されているか?(勤怠管理、給与計算、電子申請など)
- 操作性: ITが苦手な従業員でも直感的に使えるか?(無料トライアルで確認)
- サポート体制: 導入時やトラブル発生時に、手厚いサポートを受けられるか?
- 費用: 従業員数や利用機能に応じた料金体系か?初期費用と月額費用は予算に合うか?
- セキュリティ: 個人情報を守るためのセキュリティ対策は万全か?(PマークやISMS認証の有無を確認)
ステップ4:導入計画を立て、従業員へ説明する
ツールが決まったら、導入計画を立てます。誰が、いつまでに、何をするのかを具体的に決めましょう。 また、従業員への丁寧な説明も不可欠です。なぜシステムを導入するのか(目的)、従業員にとってどんなメリットがあるのかを伝え、協力を得られるように努めましょう。操作説明会などを実施するのも有効です。
ステップ5:スモールスタートで運用し、改善を続ける
いきなり全社・全業務で導入するのではなく、まずは特定の部署や業務に絞ってスモールスタートしましょう。実際に運用する中で出てきた課題や改善点を洗い出し、少しずつ対象範囲を広げていくのが成功の秘訣です。労務DXは「導入して終わり」ではなく、効果を測定し、継続的に改善していくことが重要です。
よくある質問(Q&A)
Q1. ITに詳しくない従業員が多く、新しいシステムを使いこなせるか心配です。
A1. ご安心ください。近年のクラウド型労務DXツールは、スマートフォンアプリのように直感的で分かりやすい操作性が特長です。多くの場合、無料のトライアル期間が設けられているため、本格導入前に従業員の皆さんと一緒に操作性を試してみることをお勧めします。また、電話やチャットでのサポート体制が充実しているサービスを選ぶことで、導入後の疑問点もすぐに解決できます。
Q2. 導入にかかる費用が気になります。中小企業でも負担できる金額でしょうか?
A2. 労務DXツールの多くは、従業員数に応じた月額課金制(一人あたり数百円~)を採用しており、中小企業でも導入しやすい価格設定になっています。初期費用が無料のサービスも少なくありません。また、業務効率化によって削減できる人件費やコストを考慮すると、費用対効果は非常に高いと言えます。IT導入補助金など、国や自治体の支援制度を活用できる場合もありますので、専門家に相談してみましょう。
Q3. クラウドに従業員の個人情報を預けるのは、セキュリティ面で不安です。
A3. そのご懸念はもっともです。信頼できる労務DXサービスの提供事業者は、金融機関と同レベルの強固なセキュリティ対策を講じています。
具体的には、通信の暗号化(SSL)、24時間365日のサーバー監視、不正アクセス防止システムなどを導入しています。サービスのウェブサイトで、「プライバシーマーク」や「ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証」といった第三者認証を取得しているかを確認することも、安全なサービスを見分ける一つの基準となります。
まとめ:労務DXは未来への投資。まずは小さな一歩から
本記事では、ゼロから始める労務DXをテーマに、その必要性から具体的な進め方までを解説しました。
労務DXは、単なる業務効率化ツールではありません。法改正への対応、生産性向上、人材定着といった経営課題を解決し、企業の持続的な成長を支えるための「未来への投資」です。
「難しそう」「費用がかかりそう」といったイメージで躊躇するのではなく、まずは自社の課題を一つ見つけ、それを解決するためのスモールスタートを切ってみませんか?勤怠管理のExcel集計をやめてみる、給与明細のウェブ化を試してみる。その小さな一歩が、会社の未来を大きく変えるきっかけになるはずです。
何から手をつければ良いか分からない、自社に最適なツールがどれか判断できないといった場合には、ぜひ一度、私たち社会保険労務士事務所ウェルブルにご相談ください。専門家の視点から、貴社の状況に合わせた最適な労務DXの進め方をご提案いたします。