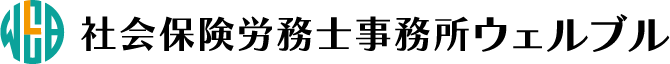従業員の「いつもと違う」様子、どう対応すべきか悩んでいませんか?
近年、働く人のメンタルヘルス不調は、企業規模を問わず、どの職場でも起こりうる課題となっています。特に、人的リソースが限られる中小企業にとって、一人の従業員の不調は組織全体に大きな影響を及ぼしかねません。
会社が適切な対応を行えば、従業員の早期回復を助け、組織への影響を最小限に抑えることが可能となります。
本記事では、社会保険労務士の視点から従業員のメンタルヘルス不調に気づいた際の初期対応、休職から復職までの具体的な支援プロセス、そして再発を防止するための職場づくりまでを網羅的に解説します。
結論から申し上げると、従業員のメンタルヘルス不調への対応で最も重要なのは、以下の3つのポイントです。
- 早期発見と迅速な初期対応
- 主治医や産業医など専門家との緊密な連携
- 計画的な復職支援プログラムの策定と実行
この記事を最後までお読みいただくことで、いざという時に慌てず法的責任を果たしながら、従業員と会社双方にとって最良の対応をとることができます。
従業員のメンタルヘルス不調、見逃してはいけない「いつもと違う」サイン
メンタルヘルスの不調は、従業員本人も気づかないうちに進行していることがあります。上司や同僚など、周りの人が「いつもと違う」サインに気づき、早期に対応へ繋げることが重要です。
行動面の変化
- 勤怠の乱れ: 遅刻、早退、欠勤が目立つようになる。特に、月曜日の朝や連休明けに休みがちになるケースは注意が必要です。
- 業務パフォーマンスの低下: 集中力が続かず、報告・連絡・相談が減る。ケアレスミスが増えたり、仕事のスピードが落ちたりする。
- コミュニケーションの変化: 口数が極端に減る、あるいは逆に些細なことでイライラして攻撃的になる。周囲との交流を避けるようになる。
身体面の変化
- 表情や様子の変化: 表情が暗く、声に張りがなくなる。身だしなみに構わなくなる。
- 体調不良の訴え: 原因のわからない頭痛、腹痛、めまい、食欲不振などを頻繁に訴える。
これらのサインは、一つひとつは些細なことかもしれません。しかし、複数のサインが重なって見られる場合は、専門家への相談を検討すべき段階と言えるでしょう。早期の気づきは、不調の重症化を防ぎ、従業員を守るだけでなく、労働契約法第5条に定められた「安全配慮義務」を果たす上でも、企業の重要な責任となります。
不調のサインに気づいたら?会社が取るべき初期対応4ステップ
従業員の不調のサインに気づいた際、会社の初期対応がその後の回復プロセスを大きく左右します。以下の4つのステップに沿って、慎重かつ迅速に対応を進めましょう。
ステップ1:声かけと傾聴(1on1ミーティング)
まずは、本人と1対1で話す機会を設けます。その際、以下の点に配慮してください。
- 場所: 他の従業員に話が聞こえない、プライバシーが確保された会議室などを選びます。
- 言葉選び: 「最近、疲れているように見えるけど、何か困っていることはない?」など、相手を気遣い、オープンに話せるような言葉を選びます。「メンタルが不調なのでは?」といった断定的な言い方は避けましょう。
- 姿勢: アドバイスや叱責は禁物です。まずは本人の話に真摯に耳を傾ける「傾聴」に徹し、本人が安心して話せる雰囲気を作ることが最も重要です。
ステップ2:産業医・専門家への相談を促す
本人の話を聞いた上で、会社として相談窓口があることを伝えます。
- 相談窓口の案内: 人事労務担当者や、産業医、社外の相談窓口(EAP機関など)があることを具体的に伝えます。
- 受診勧奨: 医療機関への受診を促すことも重要です。その際、会社が一方的に命令するのではなく、本人の健康を心配しているというメッセージを伝え、あくまで本人の意思を尊重する姿勢が求められます。
- プライバシーの保護: 相談内容や受診の事実が、本人の同意なく他者に漏れることは決してないと明確に伝え、安心感を与えます。
ステップ3:業務内容の調整
本人の状態に応じて、一時的に業務負荷を軽減する措置を検討します。これは、医師の診断書が出る前でも、会社の安全配慮義務の一環として実施すべき対応です。
- 具体的な調整例:
- 時間外労働の制限
- 業務量の削減
- 担当業務の一時的な変更(例:顧客対応から内勤事務へ)
ステップ4:休職の検討と手続き
専門医から「休職による療養が必要」との診断書が提出された場合、休職の手続きに入ります。
- 就業規則の確認: 自社の就業規則にある休職に関する規定(休職期間、期間中の給与の有無など)を確認し、本人に丁寧に説明します。
- 社会保険制度の情報提供: 休職期間中の生活を支える「傷病手当金」制度について情報提供し、申請手続きをサポートします。これにより、従業員は経済的な不安を少しでも和らげ、療養に専念できます。

【事例で解説】休職から復職までの具体的な支援プロセス
ここでは、IT企業A社に勤務するBさん(30代・システムエンジニア)の事例をもとに、休職から復職までの具体的な流れを見ていきましょう。
【事例】 Bさんは責任感が強く、重要なプロジェクトのリーダーを務めていました。
しかし、連日の長時間労働とプレッシャーから、次第に眠れなくなり、日中の集中力も低下。ある朝、どうしても出社できなくなり、心療内科を受診したところ、「適応障害」と診断され、「2ヶ月間の休職加療を要する」との診断書が発行されました。
フェーズ1:休職中のケアと連絡
A社の人事担当者は、Bさんの直属の上司と連携し、以下の対応を取りました。
- 連絡窓口の一本化: Bさんへの連絡は人事担当者に一本化し、業務に関する連絡は一切行わないように徹底。上司や同僚からの不必要な連絡が、療養の妨げになることを防ぎました。
- 定期的な状況確認: 1ヶ月に1回程度、メールで「体調はいかがですか。困ったことがあればいつでも連絡してください」とソフトな連絡を取り、Bさんが孤立しないよう配慮しました。
- 傷病手当金の申請支援: 傷病手当金の申請書類をBさん宅へ郵送し、記入方法で不明な点がないか電話で確認するなど、手続きを全面的にサポートしました。
フェーズ2:復職意思の確認と「主治医の診断書」
休職開始から1ヶ月半が経った頃、Bさんから「少しずつ回復してきたので、復職を考えたい」と連絡がありました。人事担当者は、まずは主治医の判断を仰ぐよう伝え、Bさんは主治医に相談。「就業可能な状態まで回復した」という内容の診断書を取得し、会社に提出しました。
フェーズ3:産業医による復職判定と「復職支援プラン」の作成
A社では、主治医の診断書だけで復職を決定しません。会社の安全配慮義務に基づき、最終的な復職可否は、職場の状況を理解している産業医が判断します。
産業医はBさんと面談し、「フルタイムでの勤務はまだ負荷が高い。短時間勤務から始めるのが望ましい」と判断。この意見に基づき、人事、上司、Bさん、産業医の4者で面談を行い、具体的な「復職支援プラン」を作成しました。
- プラン内容(例)
- 第1週~第2週: 1日4時間の短時間勤務(午前中のみ)
- 第3週~第4週: 1日6時間の短時間勤務
- 第5週以降: 通常勤務へ移行
- 期間中の業務: 定型的な社内業務から開始し、残業は禁止。
- 面談: 週に1回、上司との1on1面談。月に1回、産業医面談を実施。
このような計画的な復職支援は、厚生労働省が公表している出典:厚生労働省 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きでも推奨されており、再休職のリスクを低減させる上で非常に有効です。
フェーズ4:復職後のフォローアップと再発防止
プランに沿って無事に復職を果たした後も、フォローアップは続きます。定期的な面談でBさんの状態を注視し、業務負荷が過重になっていないかを確認。同時に、A社はBさんの休職をきっかけに、部署全体の業務分担や長時間労働の是正にも取り組み、再発防止に努めました。
会社が知っておくべき法的責任と予防策
従業員のメンタルヘルス不調への対応は、単なる福利厚生ではありません。企業が果たすべき法的な責任(安全配慮義務)が伴います。
安全配慮義務とは?
労働契約法第5条では、企業は従業員がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものと定められています。これを「安全配慮義務」と呼びます。メンタルヘルス不調を把握しながら放置したり、不適切な対応を取ったりした結果、従業員の症状が悪化した場合には、この義務違反を問われ、損害賠償責任を負う可能性があります。
予防が重要!職場環境の改善とストレスチェック制度
最も重要なのは、不調者を出さないための「予防」です。
- 長時間労働の是正: 勤怠管理を徹底し、時間外労働の上限規制を遵守します。
- ハラスメント対策: ハラスメント防止方針を明確にし、研修などを通じて全従業員に周知徹底します。相談窓口の設置も義務です。
- コミュニケーションの活性化: 定期的な1on1ミーティングやチームミーティングを通じて、風通しの良い職場風土を醸成します。
- ストレスチェック制度の活用: 従業員50人以上の事業場では、年に1回のストレスチェックが義務付けられています。この結果を集団分析し、職場ごとのストレス要因を把握・改善することで、効果的な職場環境改善に繋げることができます。 出典:厚生労働省 ストレスチェック制度導入マニュアル
よくある質問(Q&A)
Q1: メンタルヘルス不調を理由に、従業員を解雇できますか?
A1: 原則として、メンタルヘルス不調であることだけを理由に即時解雇することはできません。まずは就業規則に定められた休職制度を活用し、従業員に治療と回復の機会を与える必要があります。休職期間が満了してもなお業務を遂行できる状態に回復しない場合には、就業規則の規定に基づき「休職期間満了による退職」または「解雇」となるのが一般的な流れです。解雇の有効性は厳しく判断されるため、慎重な対応が求められます。
Q2: 本人が産業医との面談を拒否した場合はどうすればよいですか?
A2: 産業医面談は、本人の同意なく強制することはできません。しかし、会社には安全配慮義務があるため、なぜ面談が必要なのか(あなたの健康を守り、安心して働き続けるためのサポートであること)を丁寧に説明し、本人が抱える不安(相談内容が評価に影響するのではないか等)を解消する努力が必要です。それでも本人が拒否する場合は、その旨を経緯と共に記録しておくことが、後のトラブルを防ぐ上で重要になります。
Q3: 中小企業で産業医がいません。どこに相談すればよいですか?
A3: 従業員50人未満の事業場の場合、「地域産業保健センター」を活用することをおすすめします。労働者数50人未満の事業場の事業者や労働者を対象に、健康相談や医師による面談指導などを原則無料で提供しています。また、有料のEAP(従業員支援プログラム)を提供する外部機関と契約し、カウンセリングサービスなどを従業員に提供することも非常に有効な選択肢です。
まとめ
今回は、従業員のメンタルヘルス不調に対する会社の対応について、初期対応から復職支援、予防策までを詳しく解説しました。
従業員の心の健康問題は、もはや他人事ではありません。すべての企業が向き合うべき、重要な経営課題です。本記事で解説した3つの柱を、改めて心に留めていただければ幸いです。
- サインを見逃さない「早期発見と初期対応」
- 独断で進めない「専門家と連携した休職・復職支援」
- 不調者を出さない「予防と職場環境改善」
何よりも大切なのは、日頃から従業員一人ひとりの様子に気を配り、何でも相談しやすい風通しの良い職場風土を育むことです。それが、結果として従業員のエンゲージメントを高め、企業の持続的な成長に繋がります。
もし、対応に迷われたり、自社の体制に不安を感じたりした際には、社会保険労務士事務所ウェルブルにご相談ください。専門家として労務相談や就業規則の改訂など、貴社と従業員の皆様にとって最善の解決策を一緒に見つけていくお手伝いをいたします。