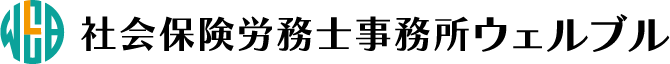「部下の成長を思って指導したつもりが、『パワハラだ』と受け取られてしまった…」
「どこからが指導で、どこからがハラスメントなのか、その線引きが分からず、コミュニケーションが萎縮している」
近年、多くの中小企業の経営者や人事担当者の方から、このようなお悩みを伺います。
ハラスメントへの社会的な関心が高まる中、企業にはこれまで以上に繊細で適切な対応が求められています。
結論から申し上げますと、ハラスメント対策はもはや単なるリスク管理ではなく、従業員が安心して能力を発揮し会社が持続的に成長するための「必要不可欠な経営戦略」です。
特に、業務上必要な「指導」と「ハラスメント」の違いを明確に理解し、全社で共有することが、全ての対策の第一歩となります。
本記事では、社会保険労務士の視点から、ハラスメントの定義、特に判断が難しい「指導」との境界線、そして中小企業が具体的に取り組むべき対策について、分かりやすく解説していきます。
なぜ今、ハラスメント対策が重要なのか?
ハラスメント対策の重要性が叫ばれる背景には、主に2つの側面があります。
- 法的義務化の拡大 2020年6月に施行された労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、大企業ではパワーハラスメント防止措置が義務化されました。そして、2022年4月からは、この義務が中小企業にも適用されています。
これは、国が企業規模を問わず、全ての労働者が尊厳を持って働ける環境の整備を企業に求めていることの表れです。
具体的な措置を講じていない場合、行政による助言・指導、さらには勧告の対象となり、従わない場合は企業名が公表される可能性もあります。
出典:厚生労働省 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! - 経営に与える深刻な影響 ハラスメントが放置された職場では、以下のような深刻な経営リスクが生じます。
- 生産性の低下: 従業員が萎縮し、自由な発言や挑戦が生まれにくくなります。
- 人材の流出: 優秀な人材が心身の不調をきたし、休職や離職に至るケースが後を絶ちません。採用コストや育成コストが無駄になるだけでなく、組織の活力が失われます。
- 企業イメージの悪化: SNSの普及により、ハラスメント問題は瞬く間に拡散する可能性があります。一度損なわれた社会的信用を回復するのは容易ではありません。
- 法的リスク: 被害者から損害賠償を求められる訴訟に発展するリスクもあります。
これらのリスクを回避し、従業員のエンゲージメントと定着率を高め、選ばれる企業となるために、ハラスメント対策は極めて重要な経営課題なのです。
ハラスメントの定義と種類
一言でハラスメントと言っても、その内容は様々です。ここでは代表的なものを確認しておきましょう。
パワーハラスメント(パワハラ)
職場におけるパワーハラスメントは、以下の3つの要素を全て満たすものと定義されています。
- 優越的な関係を背景とした言動 (例:上司から部下へ、専門知識が豊富な同僚からそうでない同僚へ)
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの (業務上の必要性がない、またはその態様が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動)
- 労働者の就業環境が害されるもの (その言動により、労働者が身体的または精神的に苦痛を感じ、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、見過ごせない程度の支障が生じること)
具体的には、以下の6つの類型が示されています。
- 身体的な攻撃: 殴る、蹴る、物を投げつける
- 精神的な攻撃: 人格を否定するような暴言、他の従業員の前での執拗な叱責
- 人間関係からの切り離し: 挨拶をしても無視する、一人だけ別室に席を移す
- 過大な要求: 到底達成不可能なノルマを課す、業務に関係ない私的な雑用を強制する
- 過小な要求: 本人の能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
- 個の侵害: 個人のプライベートな事柄に過度に立ち入る、SNSを監視する
その他のハラスメント
- セクシュアルハラスメント(セクハラ): 労働者の意に反する性的な言動により、不利益を受けたり、就業環境が害されたりすること。
- マタニティハラスメント(マタハラ): 妊娠・出産、育児休業等の利用に関する言動により、就業環境が害されること。
これら以外にも、ジェンダー(性別の役割)に関する固定観念に基づく嫌がらせ(ジェンハラ)や、介護に関する制度利用への嫌がらせ(ケアハラ)など、様々なハラスメントが存在します。

最も悩ましい「指導」と「パワハラ」の境界線
経営者や管理職にとって最も判断に迷うのが、この「指導」と「パワハラ」の境界線です。両者の違いはどこにあるのでしょうか。
ポイントは「言動の目的」と「社会通念上の相当性」です。
適正な「指導」とは?
- 目的: 部下や後輩の成長を促し、能力を引き出すこと。企業の業務を円滑に遂行すること。
- 特徴:
- 客観性・具体性: 感情的にならず、具体的な事実(いつ、どこで、何が問題だったか)に基づいて指摘する。
- 人格への配慮: 相手の人格や尊厳を傷つけるような表現は避ける。
- 改善への期待: 失敗を責めるだけでなく、どうすれば改善できるかを一緒に考え、期待を伝える。
<指導の具体例> 「先日のA社への提案書だけど、データに誤りがあったよ。正確性は非常に重要だから、今後は提出前に必ずダブルチェックするよう徹底してほしい。もし手順で分からないことがあれば、いつでも相談に乗るからね。」
「パワハラ」と判断される言動とは?
- 目的: (意図せずとも結果的に)相手を精神的に追い詰め、萎縮させ、支配すること。個人の感情を発散させること。
- 特徴:
- 人格否定: 「だからお前はダメなんだ」「小学生でもできるぞ」など、能力や存在そのものを否定する。
- 業務上の必要性の欠如: 大勢の前で長時間叱責する、過去のミスを何度も蒸し返すなど、業務上の合理性がない。
- 社会通念からの逸脱: 無視や隔離、暴力など、社会的に許容されない手段を用いる。
<パワハラの具体例> 「何度言ったら分かるんだ!こんなこともできないなんて、給料泥棒!大勢の前で土下座しろ!」
【事例で解説】グレーゾーンの判断ポイント
<IT企業B社のケース> C課長は、期待している若手社員Dさんに対し、熱心に指導を行っていました。しかし、Dさんは「課長の指導が厳しすぎる」と人事部に相談。C課長は「Dくんの成長を思ってのこと。これくらいでパワハラと言われては、何も指導できなくなる」と主張しました。
【人事部による事実確認で分かったこと】
- C課長は、Dさんの提出物に対して、他の社員がいる前で「こんなレベルの低いものを出すな」と突き返すことがあった。
- 深夜や休日に業務改善に関する長文のメールを送ることが度々あった。
- Dさんが新しい企画を提案しても、「君にはまだ早い」と頭ごなしに否定することがあった。
【判断と対応】 C課長の「成長を願う」という目的自体に悪意はなかったかもしれません。しかし、その手段(言動)は、大勢の前での叱責や業務時間外の過度な連絡など、業務上必要かつ相当な範囲を超えており、Dさんの人格を傷つけ、就業意欲を著しく低下させていました。これはパワハラに該当する可能性が極めて高いと判断。会社はC課長に指導を行うと共に、Dさんの部署異動を検討。管理職向けのハラスメント研修を改めて実施することになりました。
この事例のように、言動の背景にある「目的」だけでなく、その「態様」や「受け手の感じ方」を客観的に見極めることが重要です。
中小企業が今すぐ取り組むべきハラスメント対策4ステップ
では、具体的にどのような対策を講じればよいのでしょうか。以下の4つのステップに沿って進めることをお勧めします。
ステップ1:企業の姿勢を明確に示す
まずは、トップが「ハラスメントは絶対に許さない」という明確なメッセージを発信することがスタートです。
- 就業規則への規定: ハラスメントの禁止、懲戒処分の内容などを明記します。
- 社内報や朝礼でのトップメッセージ: 経営者の言葉で、ハラスメント対策に取り組む意義と決意を全従業員に伝えます。
ステップ2:相談窓口の設置と周知
従業員が安心して相談できる体制を整えます。
- 窓口の設置: 人事担当者や信頼できる従業員を相談員とする「内部窓口」のほか、プライバシー保護の観点から、提携先の社会保険労務士事務所や専門機関に委託する「外部窓口」の設置も有効です。
- 周知徹底: 相談窓口の存在、相談方法、相談者のプライバシーは厳守されること、不利益な取り扱いを受けないことを、ポスターや社内イントラネット等で継続的に周知します。
ステップ3:研修の実施
ハラスメントに関する知識や意識を全社で統一するための研修は不可欠です。
- 全従業員向け研修: ハラスメントの定義や相談窓口について周知し、当事者にも加害者にも傍観者にもならないための意識を醸成します。
- 管理職向け研修: 指導とパワハラの境界線、相談を受けた際の初期対応(傾聴のスキルなど)といった、より実践的な内容を学びます。
ステップ4:発生後の迅速かつ適切な対応
万が一ハラスメントが発生してしまった場合は、迅速かつ公正な対応が求められます。
- 事実関係の調査: 相談者と行為者、双方から丁寧にヒアリングを行います(プライバシー保護には最大限配慮)。
- 対応策の決定: 事実が確認できた場合、就業規則に基づき行為者への処分や配置転換を検討します。
- 被害者のケア: 被害を受けた従業員のメンタルヘルスケアや、働きやすい環境への配慮を行います。
- 再発防止策の策定: なぜハラスメントが起きたのかを分析し、研修の追加実施や業務プロセスの見直しなど、再発防止策を講じます。
よくある質問(Q&A)
Q1. ハラスメントの相談があった場合、まず何から手をつければ良いですか?
A1. まずは相談者の話をじっくりと傾聴し、安全・安心の確保を最優先してください。その場で安易に事実認定や評価をせず、「相談してくれてありがとう」という姿勢で受け止めることが重要です。次に、相談者のプライバシーを守りながら、会社として正式に調査を進める旨を伝え、今後の流れを説明します。決して一人で抱え込まず、事前に定めた手順に沿って、人事部門や経営層と連携して対応してください。
Q2. 「指導のつもりがパワハラだ」と言われないために、管理職は何に気をつければ良いですか?
A2. 以下の3点を意識してください。
- 目的の明確化: その指導が「相手の成長」や「業務改善」に繋がるものか、自問自答する。
- TPOをわきまえる: 指導は1対1で、人目につかない場所で行うのが原則です。
- 人格と行動を切り分ける: 叱るべきは相手の人格ではなく、あくまで「問題となる行動」です。「君は〇〇という行動をとったが、それは問題だ」という伝え方を心がけましょう。これを「I(アイ)メッセージ」と言い、相手を主語にする「YOUメッセージ」(君はダメだ)よりも受け入れられやすくなります。
Q3. 外部の相談窓口を利用するメリットは何ですか?
A3. 大きく3つのメリットがあります。
- 相談しやすさ: 社内の人間関係を気にする必要がないため、従業員が心理的に相談しやすくなります。
- 専門性と客観性: ハラスメント問題に精通した専門家が、客観的かつ法的な視点から公正なアドバイスを提供してくれます。
- 企業の負担軽減: 相談対応から調査、解決策の提案までを専門家がサポートするため、人事担当者の負担を大幅に軽減できます。企業の「本気度」を示すことにも繋がり、従業員の安心感を高める効果も期待できます。
まとめ
ハラスメント対策は、罰則があるから、訴訟が怖いから、といったネガティブな理由だけで取り組むものではありません。全ての従業員が互いに尊重し合い、安心して自分の能力を最大限に発揮できる職場環境を創り出すことは、企業の生産性を高め、イノベーションを生み出す土壌となります。それは、企業の持続的な成長を支える、最も重要な「未来への投資」と言えるでしょう。
指導とハラスメントの境界線を正しく理解し、全社一丸となって風通しの良い職場文化を築いていくことが、これからの時代を勝ち抜く企業にとって不可欠です。
もし、ハラスメント対策の進め方や就業規則の整備、研修の実施などでお悩みの場合は、ぜひ一度、社会保険労務士にご相談ください。
貴社の状況に合わせた、最適なサポートをご提案いたします。