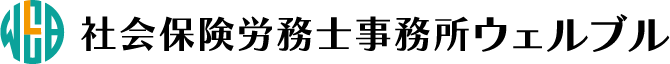「毎月のタイムカード集計に膨大な時間がかかっている…」 「残業代の計算ミスが怖くて、何度も確認してしまう…」 「働き方改革って言うけど、何から手をつければいいのか…」
中小企業の経営者や人事担当者の皆様、このようなお悩みをお抱えではありませんか?
多くの企業様から労務管理のご相談をいただく中で、勤怠管理に関する課題は特に深刻なものの一つです。
結論から申し上げます。現代において勤怠システムの導入は、単なる業務効率化ツールではなく、企業の成長を支え、労務リスクから会社を守るための『経営インフラ』です。
本記事では、なぜ今勤怠システムが必要なのか、その具体的なメリットから、気になる費用対効果、そして失敗しないための導入ステップまで、専門家の視点から分かりやすく解説します。この記事を読めば、勤怠システム導入に関する疑問や不安が解消され、自社にとって最適な一歩を踏み出すことができるでしょう。
勤怠システム導入がもたらす3つの大きなメリット
タイムカードやExcelなど手作業での勤怠管理には時間的コストだけでなく、計算ミスや不正、法改正への対応遅れといった様々なリスクが潜んでいます。勤怠システムは、これらの課題を根本から解決する事が可能です。
メリット1:圧倒的な業務効率化と人件費削減
最大のメリットは、何と言っても勤怠管理業務の劇的な効率化です。
- 自動集計による時間短縮: タイムカードの回収、Excelへの転記、残業や深夜労働の計算、有給休暇の管理…これらの手作業がすべて自動化されます。月末月初の憂鬱な集計作業から解放され、担当者はより創造的なコア業務に集中できます。
- 給与計算ソフトとの連携: 多くの勤怠システムは、主要な給与計算ソフトと連携可能です。ボタン一つで勤怠データを移行できるため、手入力によるミスがなくなり、給与計算にかかる時間も大幅に削減されます。
- ペーパーレス化の推進: 紙のタイムカードや申請書類が不要になり、保管場所や管理コストを削減できます。
メリット2:正確な労働時間把握による法令遵守(コンプライアンス強化)
労働基準法は年々改正されており、企業に求められる労務管理のレベルは高まっています。特に、時間外労働の上限規制や年5日の年次有給休暇取得義務への対応は、労基署の立ち入り調査の際にも是正勧告が出されることが多いポイントですので、すべての企業にとって喫緊の課題です。
- 客観的な労働時間の記録: ICカードやPCログ、GPSなど、客観的な記録方法により、サービス残業や不正確な自己申告を防ぎます。これは、万が一の労働トラブルの際に、会社を守るための重要な証拠となります。
- 長時間労働の可視化と抑制: 従業員ごとの残業時間をリアルタイムで把握し、上限規制を超えそうな従業員には自動でアラートを出す機能もあります。これにより、長時間労働を未然に防ぎ、従業員の健康を守ることができます。
- 法改正への自動対応: クラウド型の勤怠システムであれば、法改正が行われた際にも自動でアップデートされます。常に最新の法令に準拠した勤怠管理が可能となり、担当者の負担を軽減します。出典:厚生労働省 働き方改革特設サイト
メリット3:多様な働き方への対応と従業員満足度の向上
テレワークやフレックスタイム制、直行直帰など、働き方が多様化する現代において、従来のタイムカードによる管理は限界を迎えています。
- 場所を選ばない打刻: スマートフォンやPCから打刻できるため、テレワークや外回り営業の従業員の勤怠も正確に管理できます。
- 従業員の利便性向上: 従業員自身がいつでも自分の勤務状況や残業時間、有給休暇の残日数を確認できるため、勤怠管理の透明性が高まります。各種申請(休暇、残業など)もシステム上で完結するため、手続きがスムーズになります。
- 公平な評価制度の基盤: 正確な労働時間データは、従業員の働きぶりを公平に評価するための基礎となります。納得感のある評価は、従業員のモチベーションとエンゲージメントを高め、組織全体の生産性向上に繋がります。
【事例で解説】勤怠システム導入の費用対効果
「メリットは分かったけれど、結局いくらかかるの?」というところが最も気になるところでしょう。それでは具体的なシミュレーションと事例で、その費用対効果を見ていきましょう。
導入にかかる費用の内訳
勤怠システムには自社サーバーで管理する「オンプレミス型」と、インターネット経由で利用する「クラウド型」があります。近年の中小企業では、初期費用を抑えられ、メンテナンスも不要なクラウド型が主流です。
- 初期費用: 0円~10万円程度(導入サポートや機器購入費など)
- 月額費用: 1ユーザーあたり300円~500円程度
多くの場合、企業の規模や利用する機能によって料金が変動します。
削減できるコストと労働力のシミュレーション
仮に、従業員50名の企業で、人事担当者1名が勤怠管理に費やす時間をシミュレーションしてみましょう。
【前提条件】
- 従業員数: 50名
- 人事担当者: 1名(時給2,000円と仮定※)
- 従来の作業時間: タイムカード集計・確認に月20時間
- 勤怠システム: 月額300円/人
※担当者の月給(額面)28万程度で、会社負担分の社会保険料等を含んだ金額として仮定
【導入前の月間コスト】
- 人件費: 2,000円/時 × 20時間 = 40,000円
【導入後の月間コスト】
- システム利用料: 300円/人 × 50名 = 15,000円
- 人件費(確認作業など): 2,000円/時 × 3時間(※85%削減と仮定) = 6,000円
- 合計: 15,000円 + 6,000円 = 21,000円
【費用対効果】
- 月間の直接的なコスト削減額: 40,000円 – 21,000円 = 19,000円
- 年間の直接的なコスト削減額: 19,000円 × 12ヶ月 = 228,000円
- 年間の削減できる労働時間数: 17時間 × 12ヶ月 = 204時間
さらに重要なのは、月17時間、年間204時間という削減できた「労働時間」です。この時間を採用活動や社員研修、制度設計といった、より付加価値の高い業務に充てられると考えれば、その投資効果は計り知れません。
【導入事例】ITサービス業B社(従業員20名)のケース
B社では、営業社員の多くが直行直帰で、勤怠管理が自己申告制でした。そのため、労働時間の実態が不透明で、残業代の計算も煩雑化していました。
そこで、スマートフォン(GPS打刻機能付き)で打刻できるクラウド型勤怠システムを導入。営業担当者は出先からでも簡単に出退勤を記録できるようになり、管理者はリアルタイムで誰がどこで勤務しているかを把握できるようになりました。
導入後の変化:
- 管理の効率化: 勤怠状況の見える化により、管理者の負担が大幅に軽減。
- コスト削減: 不要な残業が減少し、残業代を10%削減することに成功。
- 従業員の意識改革: 従業員に時間管理への意識が芽生え、生産性が向上。

失敗しない!勤怠システム導入の進め方と注意点
自社に合わないシステムを選んでしまっては、せっかくの投資が無駄になってしまいます。以下の4つのステップで慎重に進めましょう。
STEP1:現状の課題と導入目的の明確化
まず、「なぜ勤怠システムを導入するのか」を明確にすることが最も重要です。 「月末の集計作業をなくしたい」「テレワークに対応したい」「残業時間を正確に管理したい」など、課題をリストアップし、導入によって達成したい目標に優先順位をつけましょう。
STEP2:自社に合ったシステムの選定
STEP1で明確にした目的をもとに、システムの機能を選定します。
- 必須のチェックポイント:
- 打刻方法: ICカード、生体認証、PCログ、GPSなど、自社の勤務形態に合っているか。
- 連携性: 現在使用している給与計算ソフトと連携できるか。
- 対応範囲: フレックスタイムや変形労働時間制など、自社の就業規則に対応しているか。
- サポート体制: 導入時やトラブル発生時のサポートは充実しているか。
- 比較検討: 2~3社のシステムに絞り込み、見積もりやデモを依頼しましょう。無料トライアル期間を活用し、実際に操作感を試してみることを強くお勧めします。
STEP3:導入準備と従業員への周知
システムが決まったら、スムーズな移行のための準備を行います。
- 就業規則の確認: システム導入に伴い、勤怠に関するルール(打刻忘れの対応など)を見直す必要がある場合は、就業規則の変更も検討します。
- 従業員への説明: 導入の目的やメリット、具体的な操作方法などを丁寧に説明する場を設けます。一方的な導入は、従業員の反発を招く可能性があります。
- データ移行と設定: 従業員情報などを新しいシステムに登録し、運用ルールに沿った設定を行います。
STEP4:運用開始と効果測定
いよいよ運用開始です。最初は操作に慣れず、問い合わせが増えることも予想されます。最初の1~2ヶ月は移行期間と位置づけ、丁寧なサポートを心がけましょう。
また、導入から数ヶ月後に「残業時間は削減されたか」「集計作業時間は短縮されたか」など、STEP1で設定した目的が達成できているか効果測定を行い、必要に応じて運用方法を見直していくことが重要です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 従業員が10名程度の小規模な会社でも、導入メリットはありますか?
A1. はい、大いにあります。小規模な企業様ほど、社長や他の業務と兼任している方が勤怠管理を担当しているケースが多く、一人当たりの業務負担が大きい傾向にあります。勤怠管理を自動化することで、その担当者が本来のコア業務に集中できるようになるメリットは、企業規模に関わらず非常に大きいと言えます。月額数千円から始められるシステムも多いため、費用対効果は十分に期待できます。
Q2. どのような打刻方法がありますか?自社に合うものが分かりません。
A2. 主な打刻方法には以下のようなものがあります。自社の業種や働き方に合わせて選ぶことが重要です。
- ICカード打刻: SuicaやPASMOなどの交通系ICカードや社員証を利用。最も一般的です。
- 生体認証打刻: 指紋や静脈、顔などで認証。なりすましを完全に防げます。
- PC・スマホ打刻: PCのログイン・ログオフや、スマートフォンのアプリで打刻。スマホを利用できない従業員がいる場合、会社でタブレットを導入し、それを利用して従業員が打刻するという企業もあります。多くの企業で導入がしやすく、特にテレワークや直行直帰が多い企業におすすめです。
- GPS打刻: スマートフォンで、位置情報とセットで打刻。外回り営業などの管理に有効です。
複数の打刻方法を併用できるシステムもありますので、事業所はICカード、営業はスマホ、といった使い分けも可能です。
Q3. 今使っている給与計算ソフトと連携できますか?
A3. 多くのクラウド型勤怠システムは、主要な給与計算ソフト(弥生給与、給与奉行、freee、MFクラウド給与など)とのAPI連携機能を備えています。できない場合でもCSVファイルで勤怠データを出力し、給与計算ソフトに取り込むことで連携が可能です。API連携が可能かどうかは、導入を検討している勤怠システムの公式サイトで確認するか、直接問い合わせるのが確実です。データ連携は、業務効率化の要となるため、必ず事前に確認しましょう。
まとめ~導入をご検討中の会社様へ~
勤怠システムの導入は、単なる事務作業の効率化にとどまりません。それは、正確な労働時間管理によるコンプライアンス強化、多様な働き方への対応、そして従業員の満足度向上を通じて、企業の持続的な成長を支えるための戦略的投資です。
手作業による勤怠管理の負担やリスクに少しでもお悩みであれば、ぜひ一度、勤怠システムの導入を具体的に検討してみてはいかがでしょうか。
もし、「どのシステムが自社に合うのか分からない」「導入の進め方に不安がある」といった場合には、ぜひ私たち社会保険労務士事務所ウェルブルにご相談ください。専門家の視点で、貴社に最適な勤怠管理体制の構築をサポートいたします。
当事務所の導入支援サービスでは、以下の内容を一貫してご提供します。
- 現状の課題ヒアリングと最適なシステムの選定・ご提案
- 導入における複雑な初期設定の代行
- 導入後の運用に関するご相談対応(システムについてのものは除く)
また、システム導入は、曖昧だった労働時間や休暇のルールを明確にする絶好の機会です。
法改正に対応し、労務リスクを未然に防ぐための就業規則の見直し・改訂もワンストップで承ります。
【勤怠システム導入支援 料金のご案内】
- 顧問契約中のお客様: 100,000円(税別)~
- スポット(単発)でのご依頼のお客様: 180,000円(税別)~
※上記は目安です。料金は企業の規模や支援内容により変動します。
※就業規則の改定費用は別途お見積もりとなります。
貴社の貴重な人材と時間を未来への投資に集中させるため、面倒で複雑な勤怠管理体制の整備は、ぜひプロにお任せください。まずはお気軽にお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。